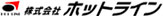普段の授業や恒例「やる気UP講座」などで、私がいつも生徒たちに呼びかけているのが、『ポジティブに考えよう』というキャンペーン。子どもたちは、ちょっとしたことですぐに「無理」とか「できない」などという言葉を口にすることが多いので、そういう生徒には、「1回につき100円の罰金をいただきます」と言って、いつも脅迫をしています。(笑)
昔、ある靴メーカーがアフリカの奥地の村に靴を売りに行く時の話。営業マンのネガ夫君が村の様子を見て、「誰も靴を履いていないので、靴は売れない」と挫折して帰国。その後、ポジ太君が再び同じ村に行って大喜び。「この村は誰も靴を履いていないから、靴がバカ売れする!」。案の定、靴は飛ぶように売れたそうです。よくあるネタ話ですが、極寒のアラスカで冷蔵庫(食品を凍らせないため)を売りまくって大儲けをした人の話も有名です。
ちょっとした考え方の違いで、結果が大きく変わる。以前に、「セレンディピティ」のお話をしましたが、プラス発想を持つか否かの違いは、学習面はもちろん、人生そのものを大きく左右すると言っても言い過ぎではないと思います。
だから、私は生徒たちにいつもこう言います。「あかんと言うたらあかん!」と。
雑草のようにたくましく【代表北村の教育ちょこっとコラム】
ヒマワリは一年草ですが、タンポポは多年草。ヒマワリは夏にしか花を咲かせませんが、タンポポは冬でも花を咲かせます。タンポポは根元あたりで切り取ってもまた葉を出しますが、ヒマワリは一度折れてしまうとおしまいです。タンポポの種は風に乗って遠くまで飛びますが、ヒマワリは落ちもしないで花のまま残っています。ヒマワリはやわらかい土でしか成長ができませんが、タンポポは固い地面やアスファルトの隙間からでも芽を出します。ヒマワリは、種をまいて育てられますが、タンポポの種をまく人は誰もいません。いわゆる〝雑草〟です。見た目での派手さはないですが、ヒマワリに比べてタンポポは、どの草花にも負けない強さを持っています。
ちょっとしたことですぐに心が折れてしまう、まるでガラス細工のような子どもたちが多くなった近頃ですが私は、日々生徒たちの顔を見るたびに、いつもこのように願っています。「君たちは、雑草のようにたくましく育ってほしい」。そうです、『挫折禁止』です!
「成績が上がってない」って、本当?【代表北村の教育ちょこっとコラム】
中学生は、ただ今期末テスト期間の真っただ中。特に受験を控えた中3生にとっては、今回のテストで内申点が最終確定するということもあって、彼らの表情は真剣そのもの。学校が終わって、夕方4時を過ぎる頃から続々とやってきて、夜も毎日数十名の生徒が最終の11時まで自主学習に取り組んでいます。
特進館学院の最近の調査では、通知表総点〔3学期末→1学期末〕が上がった生徒は全体のおよそ75~80%。にもかかわらず、保護者アンケート等の感触で、わが子の成績が上がったと認識されている方は3割程度しかありません。成績が下がったと伺って調べてみると、実は上がっていた…などということも珍しくありません。
以前にもお話ししたように、親はなかなかわが子の成果を認めず、ついついアラを探して辛口評価してしまう傾向にあります。1教科下がって4教科上がった場合でも、主観的評価では「下がった」またはせいぜい「トントン」。全教科をパーフェクトに上げない限り認めてもらえない。もしこれが日常だとしたら、毎日何時間もがんばっている子どもたちにとって、たまったものではありません。
「うちの子の成績は本当に上がっていないのか?」。主観ではなく、客観的な視点で子どもたちの成果を見極めていきたいものですね。
セレンディピティ【代表北村の教育ちょこっとコラム】
「禍福はあざなえる縄のごとし」ということわざがあります。「幸せと不幸せは表裏一体で、縄の目のように交代でやって来る」という意味ですが、果たして本当にそうでしょうか? むしろ、幸せな人はいつも幸せで、不幸な人は常に不幸に苦しんでいることが世の中多いのでは、と感じることがよくあります。
『セレンディピティ』という言葉をご存じですか? 辞書には、「珍しい宝を発見する力」、「幸運を引き寄せる能力」とあります。つまり、幸運にめぐり合うのは単なる偶然ではなく、その人の「能力」であるという考え方です。
ある製薬会社の研究員が、3つの班に分かれて「新薬D」を開発するための実験を行っていました。テーマは、「AとBを混ぜて、まずCを作る」というもの。結果は1班が成功で、2班・3班は失敗。ところが、失敗した2班は暗い顔で沈んでいるのに、3班は嬉しそうな表情。不思議に思った教授が、3班のメンバーになぜ笑っているのか尋ねたところ、「Cにならなかった液体を、さらに調べてみたら、なんと新薬Dだった」とのこと。
目先の失敗で凹まずに、プラス志向で調べた結果の大成功。これが、幸運を呼び寄せる「セレンディピティ」なのです。日本のノーベル賞科学者の多くも、このような失敗を山ほど経て、偉大な発見にたどり着いているといいます。ちなみに、念のため後で調べたら、失敗した2班にも新薬Dができていたそうです…。
男の子の夢、女の子の夢【代表北村の教育ちょこっとコラム】
第一生命保険が6日発表した「大人になったらなりたいもの」のアンケート結果によると、男の子で「学者、博士」が2位となり、前回の8位から大幅に上昇した。第一生命は「日本人のノーベル賞連続受賞の影響があるのではないか」と分析している。
男の子の1位は7年連続で「サッカー選手」、3位は「警察官、刑事」だった。前回18位の「水泳選手」が8位に浮上した。2016年夏に開かれたリオデジャネイロ五輪で日本人選手が活躍した影響とみられる。
女の子は「食べ物屋さん」が20年連続の1位となり、人気を維持した。2位は「保育園・幼稚園の先生」、3位は「学校・習い事の先生」と続いた。また「ダンスの先生、ダンサー、バレリーナ」が10位と、09年以来のトップ10入りとなった。担当者は「学校の授業にダンスが取り入れられ、身近になっている」と指摘する。
アンケートは第一生命が1989年から毎年実施しており、今回は16年7~9月に実施。全国の幼児や小学生ら1100人の回答を集計、分析した。
すべての生徒に『スポット』を当てたい【代表北村の教育ちょこっとコラム】
特進館学院は8月末に新教室を拡大し、西日本最大級の学習フロアが完成。
その中に、安物ではありますが、YAMAHAの電子ピアノを1台設置しました。
もしかしたら、「なんで塾にピアノなんか必要あるの?」などと思う方がいるかもしれませんが、実はこれには私なりのこだわりがあるのです。
ここは進学塾ですから、「勉強が得意な生徒」には、おのずとスポットが当たります。もちろん、成績上位でなくても、「すごく伸びた」生徒にも、授業や掲示物などでできる限りスポットを当てています。また、年に2~3度、アイススケートなどのスポーツ系イベントや肝だめし大会を実施し、「スポーツが得意」、「度胸がある」生徒でも、スポットが当たるように努力をしています。今回の電子ピアノは、このような試みの中で、歌や楽器など、「音楽が得意」な生徒も、時にはスポットを当ててあげたいと考えた上で設置しました。
たくさんの生徒にスポットが当たると、その子たちがプラスのオーラを発し、教室内が明るく前向きな雰囲気に包まれます。これが、特進館学院が常にこだわっている「空気」。だから、このような様々なシーンを通じて、私たちはできる限りすべての生徒にスポットを当てたいと考えているのです。
『フォロー』と『アシスト』の違いは大【代表北村の教育ちょこっとコラム】
今回は、仕事や人生における「フォロー」と「アシスト」の違い。小田真嘉さんの言葉からの引用です。
仕事も人間関係も人生も、誰かのフォローに追われている人と誰かのためにアシストできる人とでは、成果も充実度も成長度もまったく違います。
そもそもフォローとは、「問題が起きたときの事後対応」。アシストとは、「道を切りひらくための先手の攻め」。フォローに追われてばかりいたら、対応に忙殺されて前向きに考えられなくなり、次第に停滞していく。アシストができるようになるには、必要な関連情報を習得し、方向と目的をハッキリさせて、自分の役目を見出す。相手の長所が発揮される環境と条件を熟知し、どんな時に相手の短所が出てしまうのかを心得る。相手の好みや判断基準を知っておく。
そのうえで、「今、何が起きているのか?」、「相手は、何を望んでいるのか?」、その望みの先にある「本人がまだ気づいていない潜在的な欲求は何か?」、「今、自分は何をするのが最善なのか?」を問いかけながら人と向き合い、前へ進んでいく。
何だか奥が深い感じですが、私たち大人は、子どもたちに対して、常に「フォロー」ではなく、「アシスト」ができるように意識をすべきなのでしょうね。
納得いかない『塾ナビ』のランキング【代表北村の教育ちょこっとコラム】
塾検索サイト大手の「塾ナビ」をご存知ですか?「○○塾 口コミ」でネット検索すれば必ずと言っていいほど出てくるアレです。ちなみに、三田市内での塾ナビランキングには、名だたる競合塾が上位を独占していますが、どの塾もランキングポイント(最高5ポイント)は3ポイントそこそこです。そこで、「特進館学院」を調べてみると、ランキングは悲しいことに「圏外」。なのに、口コミの評価はすべて4ポイント以上の高評価。
疑問に思って、全国の大手塾の塾長先生数名に問い合わせてみたところ、「塾ナビの会員になって、多額の上納金?を運営サイトに納めないとランキングには載らない」とのこと。
これっていったい何なのでしょう? かつて、「ぐるなび」や「食べログ」などのポイントを作為的に上げる業者が大きな社会問題となったことがありますが、同じ類と思います。
公正な評価基準ならまだしも、ランキングをお金で売買するという汚い手。何も知らない純粋な保護者が、今までこのサイトを信じて大切なお子様の塾選びを行っていたと考えると、ぞっとします。保護者を騙すこういうやり方って、私には納得いきません。
なぜなら、ランキング上位の各塾から特進館学院へ、たくさん生徒が移ってきますので…。(笑)
うまいもんはうまい!【代表北村の教育ちょこっとコラム】
関西の人が、この上なく料理のおいしい店を心の底から称賛する言葉のひとつに、「うまいもんはうまい!」というのがあります。ほんとうにうまい料理は、理屈抜きにこんな言葉が口に出る。私も大阪人の端くれとして、たいへん納得できる、わかりやすい言い回しです。
私たち特進館学院は、そんな進学塾を目指しています。ご父母や生徒たちから、「ええもんはええ!」と言ってもらえたら、この上なくうれしいですから!
そのために、私たちは「授業の質」にはこだわります。しかし、授業だけでは決して成績は上がりません。それ以上に、授業で学んだ内容をしっかり〝自習〟して、理解を定着させることが、最も重要な学習方法であると考えています。
そのために、「楽しく通塾できる環境づくり」や「長時間自習していても、疲れを感じさせない空間づくり」、「気がねなく、先生と生徒が会話できるムードづくり」などにも、一生懸命力を注いでいます。これらの努力は、全国のどんな塾にも劣らないと自負しています。
このような学習環境への取り組みをあわせて、〝塾の空気〟と呼びます。私たちは、そんな〝空気〟を大切にしながら、これからも、子どもたちの夢をかなえ続ける進学塾であり続けたいと考えています。
お母さん、誉めてください!【代表北村の教育ちょこっとコラム】
先日、中間テストが終わった頃のお話し。ホールで中3のある生徒に、「すごい!5教科合計で50点以上も上がったやん」と称賛し、その後に、「お母さん、喜んだやろ!」と話しかけたところ、彼女から、「お母さん、『70点以上の教科がないからあかん』って言ってた」という返答が返ってきました。
確かに、彼女は決してお勉強が得意な生徒ではありません。5教科の平均点は50点そこそこ。だから、この春特進館に転塾し、中間テスト前は毎日のように自習室でがんばって、わからない事項は必ず質問に来てくれました。そして、見事に60点以上の平均点を勝ち取ったのです。なのに…。
彼女からの悲しい返答を聞いたとき、私は、「このお母さんって、この子が次の期末で70点平均を取っても、『80点ないからあかん』っていうのだろうなぁ…」という思いが、頭の中をよぎりました。
お母さん、お願いです!子どもたちは誉められて伸びるのです。塾の先生なんかより、子どもたち自身が一番誉めてもらいたい相手は誰なのかを、よく考えていただき、たとえ1点でも上がった教科があれば、悪い教科に目をつぶってでも、とにかくオーバーアクションで、我が子を誉めてあげてください。「すごい」、「やったね」、「うれしい」…。言葉は何でもかまいません。照れくさいなんて言わずに…。