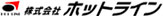頭が痛い、お腹が痛い、吐き気が…。人間には様々な苦痛があります。いずれも辛いものですが、「眠いのに眠れない」という苦痛は、そのどれよりも苦しいのではないでしょうか? 私は、中3受験生の時に書店で『短時間睡眠法』という本を読んだことがあります。いかにも受験生受けしそうなタイトルにひかれての衝動買いでしたが、これが意外と受験勉強に役立ったことを記憶しています。
本の内容を要約すれば、「人間の睡眠は約1.5時間のサイクルでできているので、その倍数分の睡眠を取ればスッキリ目覚められる」というもの。グラフをご覧ください。睡眠には「レム睡眠(浅い眠り/夢を見る状態)と「ノンレム睡眠(深い眠り)」があり、それらの睡眠が同じ周期で繰り返されます。だから、1.5時間の倍数を外れて深い眠りのタイミングで目覚まし時計を合わせてしまうと目覚めが悪くなるというわけです。
たとえば、4時間しか眠れないとわかっている時には、あと1時間だけがんばって、3時間(1.5時間×2)休んだ方が、結果的に体は楽になるという要領です。当時の私は、この理論にとても助けられました。『短時間睡眠法』。みなさんも一度お試しになってみてはいかがでしょうか?
なかなか難しい…子どもへの叱り方【代表北村の教育ちょこっとコラム】
教育に携わる人間として、『叱る』という行為は私たちの大事な仕事の一つです。でも、これがなかなか難しい。ご家庭でも同様ではないでしょうか?
うまく叱れば子どもたちはそれを機にイキイキと成長する。しかし、ひとつ間違うと取り返しのつかないことに…。そこで、叱り方の注意点『十箇条』なるものを見つけましたので少しご紹介いたします。
●子供にやってはいけない叱り方、十箇条
1. 感情的に叱る
2. 子供の言い分を聞かずに叱る
3. くどくどといつまでも叱る
4. 自分の都合で叱る
5. 両親が一緒になって叱る
6. 誰かと比べて叱る
7. 昨日と今日で言うことを変えて叱る
8. 全人格を否定する言葉や子どもを突き放す言葉を使って叱る
9. 昔のことまで引っ張り出して叱る
10. 愛情のない体罰で叱る
《映画『うまれる』シリーズ Facebookより抜粋》
いかがでしょうか? 多少耳に痛い部分もあるかもしれませんが、私たち大人がその一つひとつに気をつけて、〝正しく叱る〟ことで、子どもたちは「気づき」を得て、新たな階段を昇ることができるのだと思います。
「大人も子どもと一緒に成長していく」という謙虚な気持ちで、できる限り、実行していきたいものです。最後になりましたが、叱ったあとの『フォロー』は絶対必須アイテム。そして、『ほめる』こともお忘れなく!
「客層」の悪い日帰り温泉
仕事柄、なかなか泊まりでゆっくりと旅に出ることができないので、たまの休みに旅行気分で近場の日帰り温泉に出かけることが私のささやかな楽しみです。ここから車で1時間圏内だけでも、ステキな温浴施設がたくさんあって、わずか700円~800円で身も心もリフレッシュ。風呂上がりのかき氷は最高!
ただ、近くの温浴施設の中で「二度と行かない」と決めたところが1軒だけあります。名前は言いませんが、そこのお客はとにかくマナーが悪い。浴槽でも洗い場でも。親も子も。湯上り休憩コーナーでもそんなお客がスペースを占領し、店員も知らんふり。温浴施設なのに、癒されるどころか疲れて帰ったという最悪の経験でした…。
私は、サービス業は「客層が命」だと考えています。仮に店員がよくても利用者の質が低いと、その不快感がすべてのサービスを打ち消してしまうという恐ろしいことに…。
塾でも同じようなことが言えると思います。「割引」や「無料」などを常時売りにしている塾、「近いから」だけの塾などの「客層の低い塾」では、万一先生がよくても、成績を上げることなど不可能です。当然ながら学力レベルも低くなる。
生徒を志望校に導くためには、先生だけでなく一緒に学ぶ他の生徒との連携がとても重要。これが、特進館学院が大切にしている「塾の空気」です。私たちは、これからも「客層でも地域No.1進学塾」であり続けたいと考えています。
特進館学院の〝あいさつ〟ルール【代表北村の教育ちょこっとコラム】
特進館学院は、ただ学習指導を行うだけの塾ではなく、子どもたちへの『人間教育』もできる塾でありたいと日頃から考えています。
その中で、最も大切にしているのが「あいさつ」。あいさつで始まり、あいさつで終わる。
ですから、あいさつが素晴らしい生徒へのMVP表彰も毎月行っています。「いつも明るく元気でテキパキと行動」。あいさつはすべての行動に繋がる『要』となります。
生徒が塾に入室する時は、「こんにちは」。これは、昼夜を問わずに「こんにちは」で統一しています。帰る時には、「さようなら」。授業の開始時・終了時には、起立して「お願いします」と「ありがとうございました」。これは、スクールバスの乗降時も同様となります。保護者の方が来られた時は、「こんにちは」。お帰りの時には、「ありがとうございました」。 人間は、気分次第で良くも悪くも変化する生き物。元気で気持ち良いあいさつをお互い交せれば、その日一日を清々しく爽やかに過ごすことができ、学習に打ち込む力もパワーアップするはずです。
「あいさつは心のオアシス」。「あいさつは魔法の力(作詞:多湖輝先生)」という歌もあります。あいさつができない人は、仮に良い学校に入学しても、社会人としては務まらないと思います。だから私たち特進館学院は、これからも〝あいさつの輪〟をしっかりと拡げていこうと考えています。
『こまぎれ時間』を活用する
「時間を有効に活用する」。今さらここに標記するのも恥ずかしいくらい、すでに使い古された言葉ですが、私はこの「時間」という生き物に、けっこうこだわりながら日々を過ごしています。
大人と子ども、エライ人と平凡人、セレブと一般庶民。万人に平等に分け与えられているものが時間。誰しも一日の持ち時間は24時間のみ。だからこそ、時間は工夫しないと人生の一部を無駄にしてしまいます。
そこで、注目したいのが「3つの無駄な時間」。「待つ時間」、「探す時間」、「移動する時間」という『こまぎれ時間』です。一日の中に、数秒~数分のそんな時間が点在し、合算すると何時間にもなってしまうことが…。
そのような時間を一度見つめ直してみてはいかがでしょうか?「待つ時間を減らす」、「整理整頓を心掛ける」、「移動手段を工夫する」など…。もしくは、そのような時間を利用して他の仕事や用事を片付けてしまうという手もあります。最近は、携帯やスマホなども普及していますので可能ではないでしょうか?
最後に、私は日ごろ次のようなネガティブな言葉を人には言わないように心掛けています。「忙しい…本当に忙しい場合はその言葉すら出ません」、「疲れた(しんどい)…自分だけが苦しんでいるみたいな、独りよがりな言葉だと思います)」、「苦労した…自分で言うのではなく、他人から言われるべき言葉です」の3つ。
受験でも、仕事でも、『こまぎれ時間』を活用して、時間とうまくつき合うことが、成功に結びつく「カギ」ではないかと考えています。みなさんはどのようにお考えでしょうか?
貯金箱を割って…【代表北村の教育ちょこっとコラム】
今から30年近く前、私がまだ大阪の開成教育セミナーの社員だった当時の話。中3の女の子でYさんという塾生がいました。彼女の家庭は円満で、何不自由のない暮らしを過ごしていたのですが、その年の秋にお父様の勤める会社が倒産し、塾にも通えなくなるという状況に追い込まれていました。
そんなある日、塾の教務室に大きな紙袋を抱えた彼女が現れて、「先生。うちなぁ、どうしても冬期講習受けたいねん。うちの貯金これだけしかないけど、必ず残りは払うからお願いします!」と言うなり、「ガチャーン」と大きな音がして、ネコの貯金箱が目の前で粉々に。私たちは驚きの余り、言葉を失いました。
当時の中3生の冬期講習費は確か4万円以上。貯金箱の中には、小銭ばかりで2万円ほどあったようです。もちろん、そのお金をそのまま受け取ることなどできません。だからと言って、彼女のこの決意と気概を私たちは無駄にしたくなかったので、ご両親の了解を得て一時的に預かり、合格発表の日に「お祝い」として彼女にそのまま手渡しました。 その冬期講習で、授業を受ける彼女の目の輝きは今でも忘れません。それと、あの貯金箱が割れるシーンも…。
入塾時の通知表は、3と4混じりだったYさん。2年間で大きく伸びて、結果は大阪第1学区トップのK高校へ見事合格。母となった現在も、会社幹部として活躍しているそうです。私にとっては、甘酸っぱい思い出として心に刻まれています。
人間の可能性は限りない【代表北村の教育ちょこっとコラム】
若いお父様・お母様方はご存じないかもしれませんが、1970~80年代のテレビ・ラジオには、「プロポーズ大作戦」・「ラブ・アタック」・「素人名人会」など、お笑い系視聴者参加番組の華々しき時代がありました。当時中学生の私も、このブームに乗って、関西テレビや朝日・毎日放送などによく足を運びました。番組出演経験は、数十回。共演者は、キダ・タロー先生やさんまさんなど…。落語では、関西大会で優勝したこともあります。
これらの番組には「予選」があって、出演するには必ずその難関を通過しなくてはなりません。そんな中に、私が何度も予選会場で競い合った「H君」という学生がいました。彼は私より5歳年上で芸達者、オーラもあるなかなかの強者。彼との対戦成績は、3勝10敗くらいだったでしょうか、まさに強敵でした。
彼は大学卒業後、そのままお笑い系放送作家となって、その後数々の人気お笑い番組を世に送り出し、さらに50歳を過ぎてからノンフィクション作家への道を志すことになります。売れない数年間を乗り越えて、ついにその小説の数々は大ブレイク。作品名は、『永遠の0』・『海賊とよばれた男』・『殉愛』など…。
そうです、彼こそが、今を時めくベストセラー作家の百田尚樹さん。いくつになっても人間の可能性というのはほんとうに限りないもの。彼から自分も、大きな勇気をもらうことができた今日この頃です。
これから気になる「口臭対策」【代表北村の教育ちょこっとコラム】
ご来訪者と会話中、相手の口臭が気になって内容が全く頭に入らないことが時々…。そこで今回は、「口臭対策」について。
オーラルケアといえば、「マウスウォッシュ」などがありますが、実は口臭にはあまり効果がなく、香料で「一時的にスッキリした気がする」のが精々。刺激も強いので、口腔内の環境も悪化させるようです。また、「舌ブラシ」も使い方により唾液の質と分泌力を低下させ、さらに口臭を招く…とのこと。
では、具体的な対策法は…①正しいオーラルケアグッズを専門医に相談。②口臭体質を改善する漢方薬(煎じ薬等)を処方。③歯のかぶせ物・つめ物が正しくフィットしているかをチェック。④虫歯の治療と定期的な歯科検診。…など。
さらに、日常できる方法に「舌の位置調整」があります。舌が上顎についたままだと唾液の流れが悪くなり、口臭の原因に。そこで、「口中で舌を動かす」、「会話しない時は舌を丸めておく」、「舌先で下前歯の裏をなめる」などが有効的。舌が上顎につくのは口腔内が緊張した状態で、下にすれば緊張を緩和できるそうです。
以上、何かのお役に立てれば幸いです。
『がくりょく』をつける【代表北村の教育ちょこっとコラム】
お子様の『がくりょく』をつけてください!…「塾が何を今さら」と思われるかも? 申し上げたいのは『学力』でなく『顎力』、つまり「アゴの力」です。
「最近の子どもは頑張りがきかない」とよく言われますが、「頑張れない」、つまり歯を食いしばって我慢できず、すぐに諦めてしまう。この原因は、ハンバーグなどの柔らかい食べ物ばかり好むのでアゴの力が発達しないこと。だから、勉強も頑張れない。
歯医者さんの話ですので、間違いないと思います。ぜひ一度、ご家庭で話し合ってみてください。
たとえば、学校などでマスコミを騒がせたワードを時代別に並べてみますと、『落ちこぼれ』、『校内暴力』、『不登校』、『いじめ』、『キレる』、『恐喝』、そして最近では『殺傷事件』など、どんどんエスカレートしています。これらの社会問題は子どもたちの『顎力』、つまり『我慢力』の欠乏に負うものではないでしょうか?
子どもたちの体格は、昔よりも明らかに良いのに、『顎力』が低下している。大きな問題だと思います。スパゲティもいいけれど、たまには、かためのお食事?…もご検討されてみてはいかがでしょうか?
「誤り」を持ち越さない【代表北村の教育ちょこっとコラム】
受験学年の授業は基本的に予習が前提。問題を単に「解く」だけでなく、「答案作成力」を習熟させることが重要になる。ただ、生徒によっては、まずは「解く力を養う」ことに注力してしまう。
難易度の高い問題も多数あるが、解説時に、「よく似た問題を前にもやったけど…」と言うと、解けない生徒は「えっ、そうやったっけ?」という表情。解けた生徒は「うんうん」とうなずく。
もちろん以前とは別問題で難度も上がるが、着眼点は同じ。常に基本事項が背景。ただし、問題文からはその基本事項をもとに考えることに気づきにくい良問で、以前も「この考え方は重要だよ」と伝えている。
一度間違えることは何の問題もない。2回目に解けるか否かが重要で、そこに大きな違いが出る。解けない生徒には、もう一度「これをしっかり理解するんだ」という解説になって、答案作成力の話までなかなかたどり着けない。
「誤りを明日に持ち越さない」ことは基本中の基本。これを実践していくのはなかなか難しいけれど、諦めずに根気よく取り組むことこそが私たちの使命である。